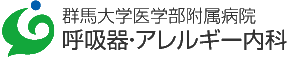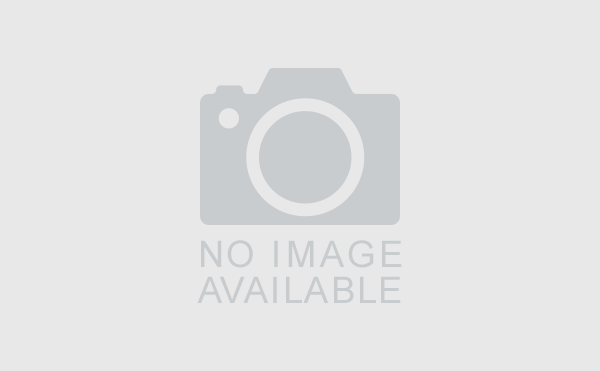2025年2月の抄読会
医学生の皆様、研修医の皆様、医会員の皆様
今月の抄読会のご案内です。 医学生、研修医の皆様にもオンラインでの開催のため、お気軽にご参加いただきたいと思っています。 今月の論文紹介をさせていただきます。
====== 2月26日(水)19:00〜 Microsoft Teams形式======
1)群馬大学医学部附属病院 前野 敏孝先生
「慢性閉塞性肺疾患に対する単一吸入器による3剤併用療法の有効性と安全性の比較:新規ユーザーコホート研究」
Feldman WB, et al. Comparative effectiveness and safety of single inhaler triple therapies for chronic obstructive pulmonary disease: new user cohort study. BMJ. 2024; 30;387:e080409.
慢性閉塞性肺疾患 (COPD) の治療において、一部の患者には 3 剤併用吸入療法(ICS/LAMA/LABA)が行われており、budesonide-glycopyrrolate-formoterolとfluticasone-umeclidinium-vilanterolが入手可能となっています。
ただし、budesonide-glycopyrrolate-formoterolとfluticasone-umeclidinium-vilanterolの有効性と安全性の比較については明らかになっていません。
今回の抄読会では、budesonide-glycopyrrolate-formoterolとfluticasone-umeclidinium-vilanterolの有効性(最初の中等度または重度のCOPD増悪)と安全性(最初の肺炎による入院)の比較について報告した論文を紹介いたします。
2)群馬大学医学部附属病院 三浦 陽介先生
「EGFR-TKI関連間質性肺疾患に対するPPIの影響について」
Wang H, et al. PPIs effect in EGFR-TKI-associated interstitial lung diseases in patients with non-small cell lung cancer. BMC Cancer. 2025 Feb 14;25(1):263.
オシメルチニブはEGFR変異肺癌の標準治療薬となっていますが、第1/2世代EGFR-TKIと比べ、薬剤性肺障害の発症頻度が高いことが報告されています。ILDの既往または併存、ICI投与歴などがそのリスク因子として報告されていますが、実地臨床ではこれらのリスク因子を持たない患者でも発症することもしばしば経験し、この点についての検討は不十分といえると思います。今回は、これまでになかったPPIがEGFR-TKIによる薬剤性肺障害の発症リスクとなりうることを示唆する論文をご紹介したいと思います。
3)渋川医療センター 村田 圭祐先生
「気管支断端瘻に対する気管支鏡的介入」
Lingli Jin, et al. Bronchoscopic interventions for bronchopleural fistulas. Ther Adv Respir Dis 2023, Vol. 17: 1–10
気管支断端瘻は気管支と胸腔が交通する病態です。多くは肺切除後に発症し、膿胸に進行し治療に難渋します。近年は吻合器の改善により発症頻度は低下していますが、一度発症すると致命的な経過をとることもある重篤な術後合併症です。ほとんどが手術後の発症であること、治療も以前は開窓術に加え大網充填術などの外科的アプローチが多かったことから呼吸器外科的な病態のイメージがありますが、最近では非侵襲的な気管支鏡による検査および治療が呼吸器内視鏡学会でも推奨されています。呼吸器外科より術後気管支断端瘻の加療を依頼される日も遠くないかもしれません。本論文は内視鏡的治療の総説的な内容となっており、現状とりうる気管支充填術のアプローチについて網羅的に比較検討されております。気管支断端瘻治療の潮流の転換点に寄せて、自験例を交え解説いたします。